(関連画像は「 」内の色文字をクリックしてご覧下さい。)
| 江戸時代⇔明治・大正・昭和(戦前)⇔昭和(戦後)⇔富貴蘭を楽しむ | |
| 富貴蘭の過去を印刷物から推測し探って見ようと、主宰者 手持ちの資料を参考に富貴蘭の歴史と神秘に迫って見ます。 (関連画像は「 」内の色文字をクリックしてご覧下さい。) |
|
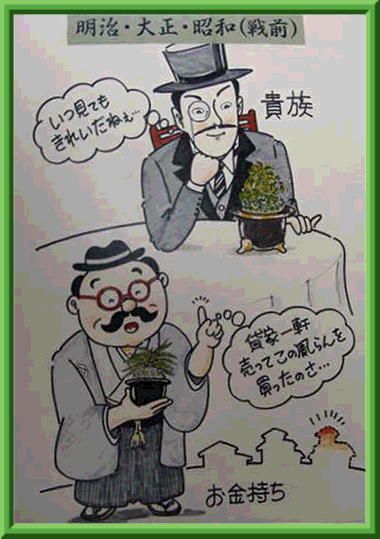 「富貴蘭見立競」(フウキランミタテキソイ) 「富貴蘭見立競」(フウキランミタテキソイ)◎古い文献に掲載のある安政2年(1855)の発行の名鑑では[風蘭見立鏡]とあり、18年後の明治6年(1873)に発行された名鑑で初めて文献に富貴蘭の名称が出て来る。 ◎現在名鑑の中心に不動の地位を築いている富貴殿もこの頃は湖東錦の西に皇覆輪の名で高隈の格下であった。 ◎また、東西に同じ名称で都覆輪の名があり、西側の都覆輪の右上に西の添え書きがあり、これが現在の西出都であり、添え書きのない方が東出都である。当然ながら東出都が格上であった。 ◎では、いつ頃から富貴蘭の名称が使われ出したかは、定かな確証は無いが、明治初期(4~5年)からと私は推測する。 ◎明治6年(1873)の富貴蘭相撲見立に「湖東錦」が最高貴品として掲載されている。 ◎明治30年(1897)浪華社中の名鑑に初めて「羆」が登場する。 ◎明治36年(1903)突如「金牡丹」の出現・愛知尾西社中の名鑑に登録されて2003年で100年を越えた。 ●番外編 「明治44年7月写」(1911)と書き込みのある「風蘭帳」もし本物 ?であれば、今 私がパソコンで書き込みをしている以上に、大変な情熱を富貴蘭に注ぎ次世代に書き残したい熱い想いが伝わって来る。 ◎真贋の程はトモカクとして、縮小して貼り付けた左上2点は葉姿を左から 幽谷殿 糸青海 孔雀丸 いずれも当時存在した人気品種の葉姿を示そうとしたものであろうか?、ここに示されている幽谷殿は幽谷錦の間違いではと想像しているのだが定かな事は不明だ。幽谷殿なる名称は、手持ちの資料には見当たらない。 ◎下段の3面の貼り付けた画像は、根の三体・付けの三体・花の三体を現している。根の色彩は劣化で生彩を欠くがルビー、青、泥と色をもって示されている。付けも三体に分類され、一文字、月、山と図絵で示している。花は、天咲き、白花、紅花とこれも色付けで分類されているが、紅花の品種名は何であったのか興味の尽きないところである。 ◎この他にも、手書きの古い ? 資料を持っているが、年代不詳で公開出来る代物ではない、今後も古い資料は出てくると思われるが、手書きの物は充分吟味の上入手されたい。 ◎ここに掲載した「園芸之友」は創刊が明治38年(1905)で、大正2年(1913)発行の園芸雑誌である。 この雑誌の中程に・加藤芳松なる篤農家は、この地に於いては富貴蘭の元祖で先祖代々これに従事し、新しい品種を作出すべく花粉の交配に努めている・・・云々の記事がある。すでにこの頃に加藤家では、富貴蘭を50、60品種 種木として栽培し、実生品種が既に完成していた事を臭わせているのである。(抜粋富貴蘭記事①・②・③・④・⑤) ◎又、価格面では・明治35年頃の大人気品の月宮殿が8分の1になった等・つい最近(2002年)我々の身近に起こっている出来事の様にも感じられる。 ◎栽培については・万年青鉢、素焼き鉢等を用いて、鉢底に木炭の小欠片を適度に入れ、芯は大きめの木炭片に水苔を巻き、その上より富貴蘭を跨がせ、水苔を被せ鉢に据える・とあり、この時代には既に水苔を用いていた様である。 ◎管理については・富貴蘭は好水草なので、多きに失せず、少なきに失せず、四季潅水に注意すべし・とあり訳が解らない。・夏期は炎熱焼くが如し、鉢は素焼き鉢に限る・とも書いている。冬場の管理では、三方壁面で、日当たりの良い向きに障子を入れる・としているのは頷ける。 ◎施肥についは・春植え替えてから、種粕を用いて土用過ぎまで2、3回与える・と書いてあるが、これは今、誰に聞いても多過ぎると云うだろう。 ◎この雑誌の発行された大正2年頃が、富貴蘭の大衰退期であった様に思う。当時の政権は、大正の政変で 山本権兵衛(ヤマモト ゴンノヒョウエ)内閣が樹立されたが、僅か1年余の短命内閣であった。 ?大正時代は改名が大流行?・大覆輪大正5年改め大典・白牡丹大正6年改め銀牡丹・金広錦大正6年改め大錦・羆親大正6年改め八千代・大江丸縞大正6年改め大正丸・天恵覆輪大正10年改め月桂冠・大典大正10年改め満月・金広錦大正10年改め日本錦・満月大正11年改め名月・白牡丹縞大正14年改め春霞・幽谷錦大正14年改め初笑・三合丸大正14年改め鳳凰・龍宮殿大正14年改め白熊・羆覆輪大正14年改め新月殿・八千代黄縞大正14年改め長壽楽(昭和12年に建国殿と改名) 等が、服部富貴園の名鑑で改名されたのである。 ここで改めて確認すべき点は、 ①満月は、大覆輪→大典→満月→名月そして現在も満月である。 ②白牡丹は、白牡丹→銀牡丹→白牡丹縞を春霞とした。現在は総散斑から一筋の縞まで白牡丹で、柄抜けが春霞である。 ③金広錦は、金広錦→大錦→日本錦、私は頷ける改名だが今は再び金広錦である。 ④八千代は、羆親→八千代で現在も流通しているが悩ましき問題の品種だ。 ⑤大江丸縞は、大江丸縞→大正丸、元の名前に戻って現在も大江丸縞で流通している。 ⑥天恵覆輪は、天恵覆輪→月桂冠、この改名がきっかけで御城覆輪が格上げで流通するようになってしまった。 ⑦幽谷錦は、幽谷錦→初笑この名は馴染まなかったのか現在も幽谷錦である。 ⑧羆覆輪は、羆覆輪→新月殿と改名した筈が、現在は変化芸として両方が流通している。 ⑨建国殿は、八千代黄縞→長壽楽としたが、後に建国殿と改名され、現在は青を建国殿、縞のある物を建国殿縞としている。 三合丸(鳳凰)と竜宮殿(白熊)は私の知る限り平成14年現在未確認品種である。 ◎この時代に、服部富貴園なる方が如何なる思惑を持って改名されたか知る由もないが、結果 妄りに改名すると混乱を招くに過ぎない事を示していると思います。 ◎昭和5年(1930)東京富貴会の名鑑で初めて皇覆輪改め「富貴殿」の名称で、名鑑の中央に座り現在も不動の地位に君臨する。 この頃から再び「裕福」な趣味家が加わり、次に示す様な豪華本の発刊に繋がったと思われる。 ◎昭和10年(1935)に発行された、カラー印刷の「原色東洋蘭図譜」この時代に、なぜこれ程豪華な本が出来たのか?、東洋蘭全般に亘る解説も深くして詳しい、編纂に関わった石井勇義先生の熱意に敬服する次第である。 さて、富貴蘭の項では最初に写真の御城覆輪に詳しく触れている。作者は池田候で、文久(1861~3)年間松阪城の石垣に着生していたものを採取などとある。他に「大八洲・金鏤閣・五十鈴川・鈴虫・弁財天・雪山・富貴殿・高隈・金牡丹・駿河覆輪・羆・鑢高隈・銀世界・白牡丹・天恵覆輪・満月・羆覆輪・玉箕(現 羽衣)・金兜・嫦娥・黒牡丹(現 孔雀丸)・水晶覆輪・曙・御旗・織姫・西出都・朝日殿・大江丸縞・太陽覆輪・青海波(現 青海)・龍鉾・金広錦・玉光覆輪・太陽殿・浪花獅子白中・針葉獅子」(写真は「青龍獅子」で単純な間違いであろう、この時代の「針葉獅子」は現在の「穂波獅子」である)の36品種がカラー写真入りで解説されている。 これら、掲載全品種を画像として愛培者名を書き込んでリンクしてある。色文字の部分をクリックして参考資料としてご覧頂きたい。この中で貴重な資料として「五十鈴川」と「羆」の画像があり、約70年前の画像を並べて比較検討出来る事は、富貴蘭愛好家にとって至福の極みである。 尚、著者 石井先生は富貴蘭については疎く、当時富貴蘭の大御所的存在の山崎天然先生の指導に基づいての記述である旨も書き添えてある。( )内に現、・・・と記した部分は、誤記、誤訳であったのかも知れない。 「京都園芸」は京都園芸倶楽部が昭和10年に発行した会報である。この会報の中で、倶楽部員 森村広太郎 なる先輩が 東洋蘭の話 として、現在も存在する蘭科園芸植物について解説している。作りに関しては前出の[園芸の友]を越える記述は無い。 ただ品種の簡単な解説と価格が書かれいる。品種の解説は一覧表の参考資料として採用、品種名と価格ノミ以下に羅列して見る。一葉幾らを念頭にご覧頂きたい(単位は円)。(抜粋富貴蘭記事①・②・③・④・⑤) 黄覆輪の部・富貴殿\80.満月\45.御旗\100.織姫覆輪\60.金甲覆輪\150.紫宸殿\130.天橋\180.天恵覆輪\25.羆覆輪\25.美雪覆輪\150.羅紗覆輪\6.連城丸\15. 白覆輪の部・駿河覆\10.水晶覆輪\150.瑞晶\30.東出都\5.西出都\7.御城覆輪\7.湖東覆輪\150.白皇覆輪\20.御劔\150. 縞物の部・大江丸縞\100.銀世界\20.御城錦\20.太陽殿\20.金兜\35.立司殿\10.墨流縞\50.金広錦\50.萬国司\60.墨牡丹縞\30. 斑物の部・曙\20.東洋殿\7.玉箕\20.春霞\20.宝船\10.浪速獅子中斑\60.真鶴\60.雪山\30.鑢高隈\7.高隈\7. ボカシ斑の部・鳳凰殿\100.新月殿\100.金孔雀\20.唐錦\30.金牡丹\20.金鏤閣\35.白鳳\10. 無地物の部・金銀羅紗\15.鯱甲龍\15.青舎合\100.孔雀丸\5.針葉獅子\5.鈴虫\5.大波青海\20.青海\10.紀州甲龍\10.伊勢矮鶏\5.浪速獅子\10.裏甲龍\10.墨流\10.乙姫\5.大鵬\5.干網\20.貴宝青\20.弁慶丸\20.金光星\50.八千代\15.麒麟樹\100. 最高逸品の部・浪速獅子白縞\1500.湖東錦\1500.大八洲\500.幽谷錦\400.羆\500.帝\300.長生殿\300.金剛殿\300.等と記載されている。 一葉単価X葉数=1本の価格と云う事になる。当時の価格で、6枚葉の湖東錦が9000円になる。今の物価に置き換えると如何ほどになるか???・・・品種の区分けに一部問題もあるが、原本に添ってそのまま書き込んで見た。 ◎昭和 7年初版昭和15年第12刷発行の「蘭と万年青」では、"「火屋」"に触れた記述があり、その内容は鼠害防止の為に籠を用いるトあり、巷に伝わる噂話では高価な富貴蘭に触れない様に被せたと云われてるが果たして如何に・・・ ◎昭和15年「趣味の会」発行の培養の秘訣である、この中に富貴蘭培養法と題して1頁記載がある。概説を除き、要点をまとめて以下に示す。(抜粋富貴蘭記事①・②) 概説・富貴蘭は俗に風蘭とも言い、深山幽谷の高い樹上に着生し、根を外部に露出伸長して空気中より水分や養分を採って生育している気根植物であります。 初夏になると花柄を出して白い花を開き芳香を放ちます。余り華美でなく本邦特有の観賞植物であります。我が国で富貴蘭を盆養し始めたのはいつ頃か詳しく分かりませんが、徳川時代には特に旺盛で開花の時、床に飾って不浄の臭気を防ぎ、又、花の香りを衣に移して芳香を賞した事が記されて居ります。 然るに、その当時は青葉のみであって只花の香りと姿を観賞したに過ぎなかったので有りますが、チョン髷時代から、飛行機の飛ぶ時代へと変還した今日の園芸の進歩発達は大したものであります。太古より伝来の青葉物に興味が薄らぎ新品種の研究努力によって縞 覆輪 虎斑 葉変り等の美術的品種は百幾十種に上って居ります。(以上は原文のまま) 植え込み方・水苔の長いものを手のひらに広げ、その上に木炭片を適当に包み込みゴムまり状にし、富貴蘭の根を跨がせ、糸を用いて固定する。鉢は特に必要ないが鑑賞のために用い、鉢底より半分程度木炭片を入れ、そこに先の富貴蘭を入れて盆栽の様に鉢縁より水苔球が盛り上がり、盆景の如く鑑賞する。 給水・富貴蘭は乾燥を好むので、春秋は2~3日、夏は毎日、冬は5~6日に一度と記している。 施肥・富貴蘭は気根植物につき、水に含む程度の肥料で間に合う、肥料は第二位にするのが最も安全、と書いています。 |
||